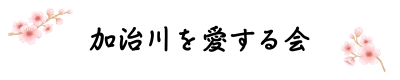加治川に設置されている案内板から加治川の桜の歴史を知ることができます。
(新潟県新発田地域振興局の許可をいただいて転載させていただいています。)
加治川の桜はじめの物語(一)
加治川の大改修工事の竣工と大正天皇の即位を記念して、大正3年、加治川の右岸左岸に合わせて6千本余のソメイヨシノ桜の幼木を植え始めました。
それから丸3年の歳月をかけ、新堤の両岸に桜並木が誕生しました。
桜の管理と保全は加治川保勝会が担当し、沿岸町村の青年会に委託されました。桜の枝打ち札打て、害虫駆除等桜の世話は大変なものでしたが、明日の郷土へ大きな希望を抱かせる心の糧でもありました。
残雪の飯豊連峰を借景として桜が連なり育っていく姿は、明日の地球の発展の象徴でもあったことでしょう。

長堤十里のさくら物語(二)
飯豊連峰の白い残雪と桜色に染まる桜堤の加治川は、春の美しさの象徴となり、たくさんの花見客で賑わいました。そして、桜の連なる長堤十里は「日本一」、「東洋一の桜」といわれるようになりました。
満開の時期には羽越線加治川鉄橋の島潟付近に花見客用の臨時停車場ができ、新潟駅や新発田駅前からは、臨時バスも運行され、両岸の桜堤は花見客でごった返しました。水面に映った満開の桜を眺めながら次々に川船が繰り出され、廻りは振舞い酒に、三味線や太鼓のお囃子、芸者衆も登場して大いに賑わいました。
その賑わいの中心は水門付近で、桜のトンネルと白い飯豊の峰々の美しさは、隆盛時には「加治川 長堤十里 世界一」とも言わしめたほどの美しさでした。
先人がつくった加治川
低い土地が広がる加治川下流の沿岸一帯は、かつて海岸砂丘に川水が行く手を阻まれ、洪水が繰り返し起きていました。このため、人々は、ここを住みやすい土地にしようと、幾たびも川の流れを変えてきました。
関ケ原の合戦以前とも伝えられる「仏島の開削」で、五十公野丘陵の南から現在の新発田市街地へ流れていた佐々木川を狭め、丘陵の北を流れて姫田川などを支流におさめる流れに切り替えました。これが加治川のはじまりです。
その後も沿岸に暮らす人々は、享保年間の「二ツ山の開削」など、機械のない時代に人手をかけて川の流れを変える工事を重ね、雪解け水や豪雨がもたらす洪水に挑み続けてきました。
そして、大正3年、ついに砂丘を貫いて日本海へ直接流れ出る加治川の分水路を掘り抜きました。こうして、現在の加治川が形づくられ、人々がこうむる洪水の苦しみは大幅に軽減されたのです。
地域を洪水から守る加治川
加治川分水路が完成したことで、洪水の発生は大幅に減りました。ところが、昭和41年と42年にこれまでにない豪雨が立て続けに襲い、堤防が決壊して下流沿岸一帯はまたしても壊滅的な被害をこうむることになりました。下越水害、羽越水害と呼ばれる二つの大きな災害です。
こうした水害が二度と繰り返さないよう、より多くの雨水を流すため川幅を拡げ、まっすぐな流れにする河川改修と、それでも流しきれない水を上流で一時的に貯めておく加治川治水ダムと内の倉ダムの建設が取り組まれました。これらの工事によって、川は毎秒最大2,000立法メートルの水を日本海へ流し出し、二つのダムに合わせて最大4020万立法メートルもの雨水を貯めることができるようになりました。これによって、沿岸一帯の洪水に対する安全性は格段に向上しています。
無念の涙の物語(三)

大正から昭和にかけて多くの人々に夢と喜びを与えてきた加治川堤の桜、それはまさしく北蒲原の大地の恵みの象徴であり、誉れ高い風景でもあり、全国に誇れる郷土の財産でした。
ところが、昭和41年7月15日に降り出した雨は、翌々日の17日には最強となり、午前11時頃に水位が4,45メートルを記録、ついに向中条の堤防が決壊したのです。いわゆる7・17水害、そして、その恐怖がまだ脳裏から離れない翌昭和42年8月28日、またしても400ミリメートルを超える豪雨により加治川が破堤。これが羽越水害です。無惨にも加治川はその姿を変え、長く愛されてきた長堤十里世界一の桜並木は、不運にも全て伐採されることを余儀なくされました。
突然襲われた水害と加治川堤の桜の伐採、それは涙無くしては語ることのできない加治川の受難の時代でもありました。
桜堤復活の物語(四)
かつて、全国的な名勝地として名を馳せ「日本一の桜」と謳われた加治川の桜並木。昭和41年・42年の連続水害による河川改修事業の際に無惨にも全て伐採されてしまいました。
しかし、失われてしまった加治川桜並木へ寄せる人々の思いは強く、美しかった桜並木をなんとか復元しようという声が高まり、新潟県では関係市町村(新発田市、旧紫雲寺町、聖籠町、旧加治川村)で組織する「加治川堤桜復元市町村連絡協議会」の要望を受け、昭和63年度より県単独で植樹帯の造成に着手しました。
さらに平成元年に、旧建設省補助事業の「桜づつみモデル事業」の認定を受け、念願であった桜並木の復元が本格的に始まりました。昭和から平成に移るこの時期が、新たな加治川桜並木の一ページとなりました。
甦る長堤十里の物語(五)
念願だった加治川の桜並木は多くの人々の協力で復元されましたが、堤防の横に盛土を行った場所に桜を植えたため、土壌は場所によってはかなり異なり、保全に大変な苦労をしました。復元した桜並木にとって一番大切なのは、生育や病害虫駆除などの保全です。
旧加治川村の「さくらの里づくりの会」では桜の里親制度を作って生育・保全活動に努めました。「加治川を愛する会」の人たちにより植樹や捕植、枝打ちや調査などの活動が行われています。
かつての、長堤十里の桜を脳裏に浮かべながら、多くの人の協力や保全活動によって、再びあでやかな姿で加治川を飾るその日が、一日でも早く訪れることを願うばかりです。
飯豊と加治川の物語(六)

陽光あふれる春の日差しの中を、ひんやりとした風が川面から流れてきます。両岸に桜色に連なる加治川の桜。滔々と流れる加治川の遥か遠くに白く連なる飯豊の峰々・・・待ちに待った雪国の春ならでは、加治川の風景です。
4月の中旬、残雪が頂きを白く染める飯豊、その前山してどっしりとそびえる二王子岳、それから借景となり、加治川の桜並木をいっそう美しく引き立てています。
加治川は新潟県北部に位置し、新発田市・聖籠町を還流し日本海に注ぐ長さ65.1キロメートル、流域面積346,3平方キロメートルの河川です。
加治川本流は新潟県及び山形県飯豊山系の御西岳(標高2012メートル)に発し、北股川、内の倉川、姫田川、坂井川などを合わせて日本海に注いでいます。流れ出る水は、新発田市から新潟市までの広大な平野部に豊な恵みをもたらしています。